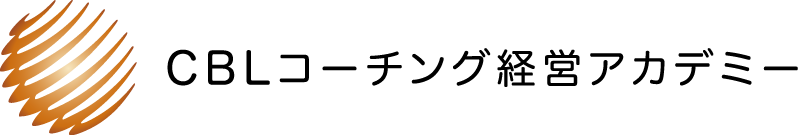「人の心」を理解し、変化を支えるために
コーチングの対話は、表面的な問題解決のためではなく、クライアントの「内的な変化」を促す営みです。A3「コーチングの心理学」では、その変化のメカニズムを理解するために、心理学的な基礎を学びます。
人の行動の背景には、思考や感情、無意識の信念、さらには過去の経験が複雑に絡み合っています。この科目では、そうした心の地図を丁寧に読み解くことで、コーチングに深みと確かさをもたらすことを目的としています。
コーチングは心理療法ではありませんが、クライアントの内面に関わるという点で心理的洞察は不可欠です。コーチが人間の心理の基本構造を理解しているほど、クライアントが自らの感情や思考を整理しやすくなり、安心して変化に向かうことができます。この講座では、心理学の理論を知識として学ぶのではなく、人間理解のレンズとして身につけることを重視します。
コーチングに活かす3つの心理学的視点
1. 認知心理学 ― 人は「事実」ではなく「意味」で生きている
人は出来事そのものではなく、それに付与した「意味」によって行動します。同じ状況でも、ある人は「挑戦」と捉え、別の人は「危機」と感じる──その違いを生むのは思考のパターン(スキーマ)です。
この科目では、クライアントの言葉の裏にある「思い込み」や「自動思考」を捉える聴き方を学びます。問いかけによって認知の枠を広げることは、クライアントが新しい視点を獲得し、行動変容へ向かう鍵になります。
2. 発達心理学 ― 変化は「成長段階」に応じて起こる
成人の成長にも段階があるという発達心理学の視点は、コーチングにおいて非常に重要です。人はライフステージや役割の変化に応じて、自己認識や価値観の構造が発展していきます。たとえば、管理職から経営層に移行するクライアントは、スキルではなく「自己と他者の関係性の再定義」という成長課題に直面します。講座では、ロバート・キーガンやジェーン・ロヴィンガーらの成人発達理論を参考に、クライアントの成長段階に応じた関わり方を考えます。
3. ポジティブ心理学 ― 強みと希望を軸に変化を促す
コーチングは「問題修正」ではなく「可能性開発」のプロセスです。
ポジティブ心理学は、人が最も力を発揮する瞬間に注目し、「強み」「感謝」「意味づけ」を重視します。講座では、強み発見ツールの活用やリフレクションを通して、コーチ自身が自分の強みを自覚することから始めます。クライアントに対しても、「何が欠けているか」ではなく「何がすでに機能しているか」に焦点を当てる対話を探求します。
「心を理解する」とは、分析することではなく寄り添うこと
心理学的理解を持つということは、相手を「分類」したり「診断」したりすることではありません。むしろ、心の多層性を理解することで、クライアントの内面に対して謙虚さと敬意を持って関われるようになります。
人は矛盾や葛藤を抱えながら成長していく存在です。コーチがそれを整えようとするのではなく、そのまま受け止めるとき、クライアントの中で自然な気づきと変容が生まれます。CBLのコーチング心理学では、「理解する」ことを関係の質を深める行為と捉えています。それは、知識ではなく在り方の一部であり、Beingの延長線上にあるものです。
次のステップへ:心理理解から構造理解へ
A3「コーチングの心理学」で養われる人間理解は、次のA4「倫理とプロフェッショナリズム」で生かされます。心理的洞察を持ったうえで、コーチとしてどのように倫理的・職業的な判断を行うかを探ることで、支援者としての成熟がさらに深まります。
人の心を知ることは、他者を操作するためではなく、他者を尊重し、信頼を基盤に変化を支えるための知恵です。コーチングの心理学は、その知恵を“実践知”として身につけるための、大切なステップなのです。
国際コーチング連盟認定マスターコーチ(MCC)
日本エグゼクティブコーチ協会認定エグゼクティブコーチ
五十嵐 久