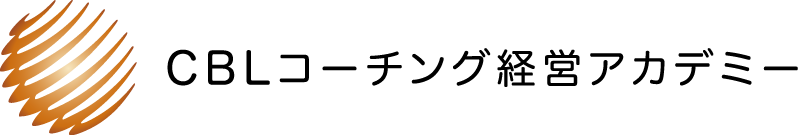信頼と安全を守る「関わりの線引き」
コーチングが真に機能するためには、クライアントが「安心して自分を語れる場」であることが欠かせません。その安全を支えるのが、コーチとクライアントの間に存在する「境界」です。
A2「コーチングの境界」では、コーチとして守るべき関係性の線引きを多角的に理解し、倫理・心理・契約・感情などの側面から、プロフェッショナルとしての成熟を深めます。
コーチングは“対話を通じて変化を生む関係性”であり、その中では信頼、依存、期待など多様な感情の動きが生じます。だからこそ、境界をあいまいにしてしまうと、支援が支配に変わり、信頼が崩れてしまう危険性もあります。
本科目では、国際コーチング連盟(ICF)の倫理規定を軸に、コーチングが他の支援職(カウンセリング、メンタリング、コンサルティング、ティーチングなど)とどう異なるのかを明確に区別し、クライアントの自立と成長を守るための「健全な距離感」を学びます。
コーチングにおける3つの境界意識
1. 関係性の境界 ― 「誰の課題なのか」を明確にする
コーチはクライアントの人生や仕事に深く関わりますが、その課題の所有権は常にクライアントにあります。コーチが「助けたい」「導きたい」という気持ちを強く持ちすぎると、無意識にクライアントの領域に踏み込んでしまうことがあります。
この講座では、「支援」と「介入」の違いを明確にし、クライアントの主体性を尊重しながら伴走する姿勢を磨きます。キーワードは「エンパワーメントEmpowerment」。コーチは答えを与える人ではなく、答えが生まれる場を整える人であることを理解します。
2. 役割の境界 ― コーチとしての専門的立場を保つ
職場・組織・チームなど複数の利害関係者が関わる場では、「誰のためのコーチングか」を常に明確にしておく必要があります。特にエグゼクティブや企業支援では、スポンサー(依頼者)とクライアント(被支援者)が異なることが多く、報告の範囲・契約内容・守秘義務の線引きを誤ると信頼関係を損なうリスクがあります。
本講では、契約設計やフィードバック報告の具体的なケースを扱いながら、職業倫理と実務判断のバランスを学びます。
3. 感情の境界 ― 感情移入ではなく共感で関わる
コーチングでは、クライアントの感情を受け止めながらも巻き込まれず、穏やかに関わる力が求められます。これは冷静さではなく「共感的距離感」のスキルです。
感情の境界を保つとは、自分の内側に生まれる感情を意識的に観察しながらも、それに支配されないことです。感情の気づきを促すリフレクションやケーススタディを通して、自己感情のセルフマネジメントを学びます。
境界が生む「自由な関係性」
一見すると境界は「距離を置くこと」に見えるかもしれません。
しかし、境界があるからこそ、コーチとクライアントの関係は自由で創造的になります。
お互いの立場と責任が明確だからこそ、クライアントは安心して挑戦でき、コーチは純粋に相手の可能性を信じることができます。
CBLが掲げる“幸せ共創社会”の実現においても、健全な境界は不可欠な基盤です。
それは「私」と「あなた」の間に透明な空間を生み、そこに本質的な対話が芽生えるからです。
次のステップへ:境界を理解した上で、心を開く
A2「コーチングの境界」で学ぶのは、単なる規律ではなく、信頼を育む土台です。
この学びを通じて、「守ること」と「関わること」を統合し、より自由に、より誠実にクライアントと向き合えるようになります。
次のA3「コーチングの心理学」では、こうして確立した関係性を背景に、人の心の動きや無意識のプロセスを理解していきます。
国際コーチング連盟認定マスターコーチ(MCC)
日本エグゼクティブコーチ協会認定エグゼクティブコーチ
五十嵐 久