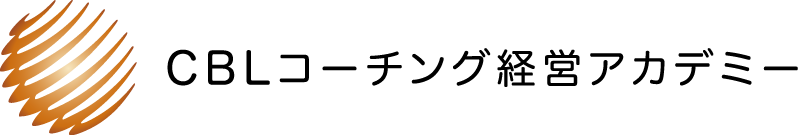コーチングの信頼を支える「見えない力」
優れたコーチングは、目に見えるスキルや知識だけで成り立っているわけではありません。その根底には、クライアントとの信頼関係を守るための「倫理」と、専門職としての自覚を体現する「プロフェッショナリズム」という、揺るぎない軸が存在します。
A4「倫理とプロフェッショナリズム」は、コーチングを「職業」としてだけでなく「人としてのあり方」として捉え直す講座です。
倫理は、何をしてよいか・悪いかを判断するための規則ではなく、クライアントの尊厳と自由を守るための約束です。一方でプロフェッショナリズムは、その約束を日々の行動で示すことです。この講座では、国際コーチング連盟(ICF)の倫理規定をベースに、事例や対話を通して、倫理的判断力とプロとしての誇りを養います。
コーチとしての信頼を築く3つの軸
1. 守秘義務 ― クライアントの安心を守る根幹
コーチングにおいて最も重要な信頼の基礎は「守秘義務」です。クライアントが安心して話せるのは、「この人には何を話しても大丈夫だ」と感じられるからです。倫理規定における守秘義務とは、単に情報を外に漏らさないという意味ではなく、クライアントの内面に対する敬意の表現です。
この講座では、組織契約やスポンサー付きコーチングのように、第三者が関与する場合の具体的な報告範囲・線引きもケースを通じて学びます。
2. 境界と責任 ― 関係を曖昧にしない姿勢
A2「コーチングの境界」で学んだ概念をさらに深め、倫理的な判断としての「線引き」を探求します。たとえば、コーチがクライアントの決断に影響を与えすぎてしまうケース、コーチ自身の価値観が無意識に会話に入り込むケースなど、現場では微妙な判断が求められます。倫理とは、そのようなグレーゾーンに立ったときに、何を大切にし、どんな行動を選ぶかという内的指針です。講座では、ディスカッションやロールプレイを通じて、倫理的ジレンマへの対応力を養います。
3. プロフェッショナリズム ― 態度と行動に表れる専門性
プロフェッショナリズムとは、肩書きではなく姿勢です。「どんな状況でも誠実に」「クライアントの利益を最優先に」「学び続ける姿勢を持つ」──そのような日常的態度が、結果として専門職としての信頼を形成します。
ICFでは、継続的学習(Continuing Coach Education)を義務づけていますが、CBLアカデミーでは「学び続けること自体がBeingの表現である」と捉えます。
つまり、プロフェッショナリズムとは知識の更新ではなく、自己の更新でもあるのです。
倫理は「縛り」ではなく「自由を守るもの」
倫理という言葉には、堅苦しさや制約のイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし本来の倫理は、クライアントとコーチの双方が安心して探求できる自由の枠組みをつくるものです。倫理があるからこそ、クライアントは恐れずに本音を語り、コーチは信頼を背に勇気ある問いを投げかけることができます。倫理はコーチングの創造性を妨げるものではなく、それを支える土台なのです。この講座では、倫理を「守るべき規範」ではなく、「生き方の選択」として捉えることを学びます。
自分自身の価値観や判断軸を明確にしながら、「私は何を大切にしてコーチングをしているのか」という問いに立ち返ります。
次のステップへ:プロとしての自覚をもって構造を学ぶ
A4「倫理とプロフェッショナリズム」で確立した倫理的・職業的自覚は、次のA5「コーチングの構造」で活かされます。倫理を軸に持つことで、コーチングセッションを設計するときにも、クライアント中心の構造を意識できるようになります。
本講座を通じて、“技術を持つ人”から“信頼される専門家”へと進化していきます。
コーチングという実践は、言葉ではなく「在り方」で信頼を築く営みです。A4はその核心を照らす時間であり、CBLアカデミーが育てたい“真に誠実なプロフェッショナル”への扉となります。
国際コーチング連盟認定マスターコーチ(MCC)
日本エグゼクティブコーチ協会認定エグゼクティブコーチ
五十嵐 久